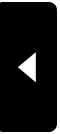この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。
夏のごあいさつ
日頃の感謝をかたちに変えて
「お中元」は、日頃お世話になっている人に対し、夏のあいさつをかねて品物を贈ることをいいます。
もともとは中国の道教の「三元節」の一つで、日本のお盆と結びついて定着したものです。
古代中国では、旧暦の1月15日を「上元」、7月15日を「中元」、10月15日を「下元」として、この「三元」の日には神様に供物を献上して祝うという習慣がありました。
なかでも7月15日の「中元」は日本のお盆の行事と重なり、親戚や知人、仕事関係でお世話になっている人などに品物を贈るという風習が定着しました。

贈答品としては、祖霊へのお供えものとして、ちょうちんや線香、そうめんなどの麺類、白米、お菓子、くだものなどを贈ることが古くからのしきたりだったようです。
現在はこうした傾向は薄れています。
ついつい品物の見栄えや華やかさに心がいきがちですが、相手への感謝の気持ちを込めて、相手に喜んでもらえるよう工夫して贈りたいものですね。
「お中元」は、日頃お世話になっている人に対し、夏のあいさつをかねて品物を贈ることをいいます。
もともとは中国の道教の「三元節」の一つで、日本のお盆と結びついて定着したものです。
古代中国では、旧暦の1月15日を「上元」、7月15日を「中元」、10月15日を「下元」として、この「三元」の日には神様に供物を献上して祝うという習慣がありました。
なかでも7月15日の「中元」は日本のお盆の行事と重なり、親戚や知人、仕事関係でお世話になっている人などに品物を贈るという風習が定着しました。

贈答品としては、祖霊へのお供えものとして、ちょうちんや線香、そうめんなどの麺類、白米、お菓子、くだものなどを贈ることが古くからのしきたりだったようです。
現在はこうした傾向は薄れています。
ついつい品物の見栄えや華やかさに心がいきがちですが、相手への感謝の気持ちを込めて、相手に喜んでもらえるよう工夫して贈りたいものですね。
一年に一度の・・・
夏至後15日目で、「小暑」と呼ばれています。
梅雨の晩期にあたり、集中豪雨に見舞われることもありますが、梅雨が明ければ本格的な暑さが始まります。
また、蓮の花が咲き始め、鷹ノ子が巣立つ時期とされています。
 そして、今日は「七夕」。
そして、今日は「七夕」。
牽牛と織女が、7月7日の夜に天の川を渡って、年に一度だけ会うことを許された日です。
この日の夜、2人が天の川を渡れるように、カササギが羽を重ね橋を架けるという伝説があります。
彦星と織姫が踏み渡るため、七夕になるとカササギの首の毛が抜け落ちるといわれているとか・・・。
今日はあいにくの梅雨空で、一年に一度の2人の出会いを見ることはできませんが、晴れた日に東の夜空を見てください。
大きな宇宙で、織女星(ベガ)と牽牛星(アルタイル)、はくちょう座(デネブ)が作る「夏の大三角形」を見ていると、いい気分転換になるかもしれませんよ。
梅雨の晩期にあたり、集中豪雨に見舞われることもありますが、梅雨が明ければ本格的な暑さが始まります。
また、蓮の花が咲き始め、鷹ノ子が巣立つ時期とされています。
 そして、今日は「七夕」。
そして、今日は「七夕」。牽牛と織女が、7月7日の夜に天の川を渡って、年に一度だけ会うことを許された日です。
この日の夜、2人が天の川を渡れるように、カササギが羽を重ね橋を架けるという伝説があります。
彦星と織姫が踏み渡るため、七夕になるとカササギの首の毛が抜け落ちるといわれているとか・・・。
今日はあいにくの梅雨空で、一年に一度の2人の出会いを見ることはできませんが、晴れた日に東の夜空を見てください。
大きな宇宙で、織女星(ベガ)と牽牛星(アルタイル)、はくちょう座(デネブ)が作る「夏の大三角形」を見ていると、いい気分転換になるかもしれませんよ。
半夏生(はんげしょう)
「半夏生」は、夏至から数えて11日目の7月2日を指します。
 このころに半夏(カラスビシャク)という名前の薬草が生えるため、こうした名前がついたといわれます。
このころに半夏(カラスビシャク)という名前の薬草が生えるため、こうした名前がついたといわれます。
この時期は田植えにちょうどよく、夏至と半夏生の間に田植えをすませるといいとされました。
また「半夏生には毒気が降るので前夜から井戸や泉に蓋をする」とか、「地が毒気を含むのでこの日にとった野菜を食べてはいけない」などという迷信もあるようです。
農家では、この日の天気によって豊作か凶作かを占う風習もあり、農業を営む人たちにとっては、大切な目安となる日だったのです。
今日は、涼しくすごしやすい一日でしたが、もう少しうっとうしい日が続きます。
どうぞ、ご自愛ください。
 このころに半夏(カラスビシャク)という名前の薬草が生えるため、こうした名前がついたといわれます。
このころに半夏(カラスビシャク)という名前の薬草が生えるため、こうした名前がついたといわれます。この時期は田植えにちょうどよく、夏至と半夏生の間に田植えをすませるといいとされました。
また「半夏生には毒気が降るので前夜から井戸や泉に蓋をする」とか、「地が毒気を含むのでこの日にとった野菜を食べてはいけない」などという迷信もあるようです。
農家では、この日の天気によって豊作か凶作かを占う風習もあり、農業を営む人たちにとっては、大切な目安となる日だったのです。
今日は、涼しくすごしやすい一日でしたが、もう少しうっとうしい日が続きます。
どうぞ、ご自愛ください。
どっこいしょ
 7月1日は霊峰冨士の山開き。
7月1日は霊峰冨士の山開き。各登山口には、白装束に金剛杖を持った行者が全国各地から集まり、「六根清浄(ろっこんしょうじょう)」と唱えながら登り始めます。
日本では昔から山岳信仰が盛んで、山は神聖視されていたため、通常、霊山には山伏や僧侶しか立ち入ることができませんでした。
その禁を解き、夏の一定期間に限って一般の人々にも入山を許可するようになったのが山開きです。
「六根清浄(ろっこんしょうじょう) 」
六根とは「眼耳鼻舌身意(げんにびぜつしんに)」(「意」は心を指す)を総称する仏教語で、身体の器官とその働きを表します。
六根清浄には、山の自然と一体となって六根を清らかにし、見るもの聞くものなどにとらわれた心を無にするという意味が込められています。
私たちが日頃よく使う「どっこいしょ」という掛け声は、この六根清浄がなまったものといわれています。
禊(みそぎ)
穢(けが)れとは、不潔なもので死をもたらす危険なもののことを指します。
古来、さまざまな災厄の根源となる穢れは、祓(はら)いや禊(みそぎ)をすることで取り除くことができると考えられていました。
水で邪気を浄化する
禊は「水・火・塩・幣(ぬさ)」などによって行なわれますが、なかでも最も霊力が強いとされるのが水による「禊」です。
水の霊力を信じていた昔の人々は、6月になると暑気払いをかねて氷や氷に見立てた餅などを食し、新たな半年に備えるための邪気祓いを行ないました。
 京都には、この時期「水無月」という、白い外郎(ういろう)生地に小豆をのせた和菓子を食べる習慣があります。
京都には、この時期「水無月」という、白い外郎(ういろう)生地に小豆をのせた和菓子を食べる習慣があります。
水無月の上部にある小豆は悪魔払いの意味があり、三角の形は暑気を払う氷を表しているといわれています。
あと5日で6月も終わります。
甘いものは苦手ですが、残りの半年を元気に過ごせるよう、「水無月」を食べて「禊」をしようかな。
その考えこそ、甘いですか・・・?
古来、さまざまな災厄の根源となる穢れは、祓(はら)いや禊(みそぎ)をすることで取り除くことができると考えられていました。
水で邪気を浄化する
禊は「水・火・塩・幣(ぬさ)」などによって行なわれますが、なかでも最も霊力が強いとされるのが水による「禊」です。
水の霊力を信じていた昔の人々は、6月になると暑気払いをかねて氷や氷に見立てた餅などを食し、新たな半年に備えるための邪気祓いを行ないました。
 京都には、この時期「水無月」という、白い外郎(ういろう)生地に小豆をのせた和菓子を食べる習慣があります。
京都には、この時期「水無月」という、白い外郎(ういろう)生地に小豆をのせた和菓子を食べる習慣があります。水無月の上部にある小豆は悪魔払いの意味があり、三角の形は暑気を払う氷を表しているといわれています。
あと5日で6月も終わります。
甘いものは苦手ですが、残りの半年を元気に過ごせるよう、「水無月」を食べて「禊」をしようかな。
その考えこそ、甘いですか・・・?